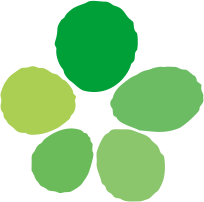本日のお楽しみ会では,密にならないように2つの活動室を開放し,感染予防対策をしたなかで実施しました。まず始めに,子どもたちの好きな鬼滅の刃やパプリカを職員が楽器演奏すると,演奏に合わせて歌ったり手を叩いたりととても大喜びでした。

次に,各クラスの子どもたちでみんなの前でダンスや歌,劇などの発表をしました。ほしグループは職員と一緒にサンタになってツリーの飾りつけをしました。前に出て発表する機会が少ない子どもたちは,恥ずかしそうにしていましたが,時折笑顔をみせながらツリーを上手に飾ることができました。


そらグループは,大きなかぶの劇で,みんなで力を合わせてかぶを引っ張りました。最後の掛け声では,劇を見ている子どもたちもみんなで「うんとこしょ,どっこいしょ!」と言って大きなかぶを引き抜くことができました。そらグループみんなで並んで引っ張る姿が,とても可愛らしかったです。

にじグループは,おどるポンポコリンのダンスと,おもちゃのチャチャチャの歌を披露しました。曲に合わせてリズムよくしゃがんだり跳んだりして,身体をいっぱい動かしました。歌では,恥ずかしそうにしながらもお友達と顔を見合わせて笑うなど,一生懸命歌う姿がとても素敵でした。

2歳児から年長児まで幅広い年齢の子どもたちがいますが,グループ全体で実施したお楽しみ会を通して,お友達に興味や関心を持つことができた楽しい機会となりました。これからも,コロナに負けず子どもたちのたくさんの笑顔がみられるように,様々な工夫をしながら思い出作りをしていきます。(二見)