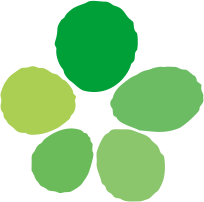今回は,信号の色が変わるまでに信号を渡り終える意識をもてるようになることや地域の方に挨拶をすることで地域の人との交流を図ることをねらいに園外散歩を行いました。
めばえから花屋前の横断歩道を渡り,仁田尾バス停付近まで歩いて再度横断歩道を渡ってめばえに帰るというルートで取り組みました。
出発前に,活動室にていくつかの約束事や交通ルールを確認しました。「ペアで手を繋ぎ,2列で歩くこと」や「横断旗やスズランテープから出ないこと」,「車や自転車に気を付けること」等複数の約束事をしました。「信号の止まれは何色?」,「信号を渡る時は何をしたら良いかな?」,「地域の人に会ったらどうする?」等,クイズ形式で楽しく交通ルールを学ぶことができました。

めばえを出発すると,早速地域の方に出会い「これから散歩行くよ!」,「行ってきます!」と元気よく挨拶をすることができました。「頑張ってね。」と言われ,少し照れる子どもたちでしたが,自分から挨拶をする姿に成長を感じました。

押しボタン式の信号を渡る際は,就学に向けて年長児を中心に実際にボタンを押して青になったことを確認し,落ち着いて信号を渡り切ることができました。「渡る前は右,左,右を見ようね。」,「手を挙げて渡ったら格好良いね。」と手本を提示しながら声掛けを行うと「僕もできるよ!」,「私も!」と得意気に教えてくれる子どもたちでした。
時折,大好きなトラックやバイクに興奮して列から離れそうになる姿もありましたが「離れないようにね。」,「ゆっくり歩こう。」等とペアで声を掛け合いながら約束事を守って取り組むことができました。


めばえに到着すると「疲れたけど,小学生になるから最後まで頑張りました。」や「大きな道路を歩いたことが楽しかったです。」等,1人1人感想を発表することができました。

園外散歩を通して,約束事や交通ルールを守る大切さを学ぶだけでなく,体力や危険予知能力を高めたりペアで協力したりする経験にもなりました。また,園外散歩は就学に向けての取り組みとして取り入れています。安心して通学ができるようにルートや内容を工夫しながら今後も取り組んでまいります。
感染症の影響で地域の方々との交流や園外での活動が少なくなっていますが,子どもたちの成長に繋がる様々な経験ができるような活動を提供していきます。
(藤谷)