朝,元気に通所してきた子どもたちの1日は,リトミックから始まります。身体をほぐしたり気持ちの発散をしたりして,1日の活動への意欲を高めます。今回は,にじグループのリトミックの様子をお伝えします。


はじめは,「さんぽ」,「おうま」,「かたつむり」等の音楽に合わせて身体を動かします。「さんぽ」のときは前歩きや後ろ歩き,「おうま」のときは四つ這い,「かたつむり」のときはほふく前進等,不規則に変わる音楽に合わせて動きを変化させるため,周りの音や声をよく聴くことが必要です。


次に,お友達や職員と手を繋いで輪になり「おどるポンポコリン」の音楽に合わせて踊ったり,他児と音楽に合わせてじゃんけんをする「じゃんけん貨物列車」をしたりします。ここでは,身体を動かすだけでなく,他者を意識しながら動くペースを合わせたりルールを守って活動に取り組んだりすることが必要です。クラスが新しくなった4月当初は,恥ずかしさや緊張からか,お友達や職員と手を繋いだり肩を持ったりすることに抵抗があった子どもたちも,今では笑顔で楽しくお友達と関わることができるようになりました。また,お友達が転ばないようにゆっくり歩いたり回ったりと優しい姿もみられます。


十分に身体を動かすことができたら,ゆったりとした音楽を聴きながらリラックスをします。たくさん身体を動かした後に横になることで,気持ちを落ち着かせたり静と動の切り替えをしたりすることに繋がります。

最後は,タンバリンを鳴らしておしまいです。タンバリンを鳴らすことで,1つの活動が終わったことへの達成感や満足感を味わうことができます。また,次の活動への意欲にも繋がります。


これからも,身体を動かし,元気いっぱい過ごしましょう!(工藤)
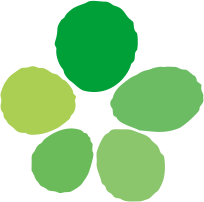





























 (米山)
(米山)











