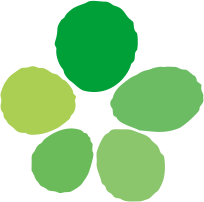暑い日が続く中、今年初めての水遊びを行いました。今回は水に触れることで季節を感じ、友達と道具を共有することをねらいに、金魚すくいの活動に取り組みました。
まずは、ルールや道具の使い方を確認すると、子どもたちからは「したことあるよ。」、「できるよ。」とたくさんの言葉が出てきました。支援者が金魚すくいの見本を提示すると、「早くしたい。」とウキウキした言葉が聞こえてきました。道具の使い方以外にも水あそびに参加する際の約束事も確認しました。テラスは歩く、水をかけてほしくない時は「しないで。」と伝えるなど友達と関わる上での約束事も意識して参加することができました。
次に、グループ対抗で金魚すくいに取り組みました。時間内にたくさんの金魚やあひるを掬い、数で勝敗を決めます。順番を話し合いするよう伝えると「何番がいい?」「僕は1番。」と友達に尋ねたり伝えたりとそれぞれです。じゃんけんで決める子もいましたが、スムーズに順番が決まり、金魚すくいゲームの始まりです。



「〇〇くん頑張れ。」とグループの友達を応援したり「たくさん取るぞ。」と意気込んだり、たくさん掬うため慎重にポイを扱ったりとたくさんの子どもの姿を見ることができました。20秒、40秒と時間を徐々に伸ばしながら取り組みましたが、タイマーが鳴るとポイを定位置に置き、数を数えることを待つ姿もみられ、メリハリのある動きも意識することができました。
最後まで約束を守りながら活動に参加することができ,水あそびを通して季節感を味わったり道具の使い方を覚え,物を共有したりなど様々な経験を重ねることができました。8月も水あそびを予定しています。熱中症に気を付けながら様々な活動を提供していきたいと思います。(竹之下)