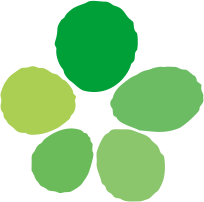本日の活動では、氷の冷たい感触を確かめながら、氷で様々なあそびの展開を楽しむことをねらいに氷あそびをしました。まずは、牛乳パックに水と玩具を入れて凍らせた大きな氷をみんなで玩具を取り出すあそびをしました。氷の中に組み込まれている玩具をみんなで興味深々に見たり触ったりして感触を楽しみながら取り出そうとしていました。冷たい感覚が苦手な子どもさんの興味のある玩具を入れたことで少しだけ触ることができました!また、氷に組み込まれているアヒルの玩具をみて「助けて~。」と言って助け出そうと頑張って溶かす様子もあり微笑ましかったです。


次の展開として、色水を凍らせて氷のクレヨンを使ってお絵描きをしました。製氷機に入っているカラフルな氷を見て目をキラキラさせながらすぐに手を伸ばす子どもたち。

画用紙に色付きの氷を擦り付けるとクレヨンのように色が付きみんな無我夢中でお絵描きをしていました。他には氷の感触が苦手な子どもさんもいることと、持ちやすいようにストローを刺した氷にして提供するとストロー部分を持ちながら不思議そうに観察したり手に色を付けてみたりしていました。
今回は氷に興味をもったり触ることに挑戦したりできるように玩具を取り出すあそびとお絵描きの2つのあそびを展開しました。これからも様々な素材や物に挑戦して触れたり興味に繋げたりできるように遊び方や提供の仕方を工夫しながらあそびの幅をひろげていきたいです。(箱丸)